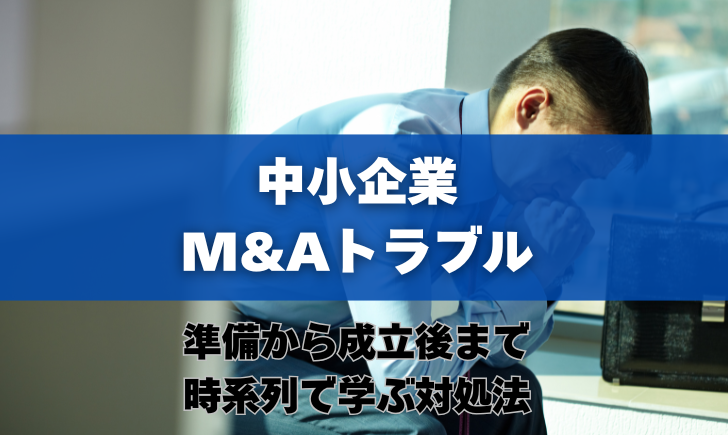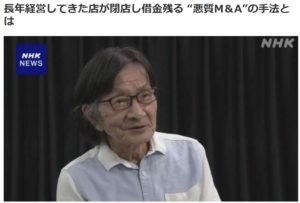M&Aは、企業が事業拡大するための有力な手段として期待されています。
一方で、事業を売却する側にとっては、非常に大きな決断を伴います。
売却が成功すれば、事業の新たな可能性を買い手に引き継ぎ、オーナーとしての責任も全うできるでしょう。
しかし、予期しないトラブルに巻き込まれるリスクも避けられません。
この記事では、事業売却時に直面しやすいトラブルについて、わかりやすく解説します。
最後までお読みいただくことで、こうしたトラブルを未然に防ぐための具体的な方法をご理解いただけるでしょう。
M&Aに不安を感じている経営者の方は、ぜひ最後までお読みください。
増加の一途!中小企業M&Aトラブル8選
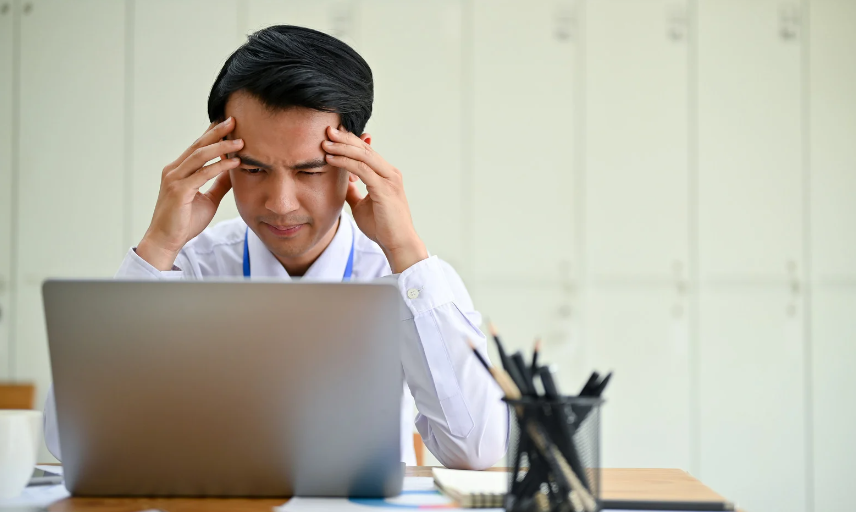
中小企業におけるM&Aのトラブルが増加しています。
2024年に報道された事例によると、
- 喫茶店の経営者が、M&A仲介業者から紹介された会社に店を譲渡
- その後、買い手が賃料を滞納
- 従業員が次々に退職
最終的には、店が閉店に追い込まれるトラブルが発生しました。
出典:NHK 長年経営してきた店が閉店し借金残る “悪質M&A”の手法とは
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240930/k10014596221000.html
このようなケースでは、買収側が資産のみを目的とし、事業継続の意思がないまま放置される「悪質なM&A」の被害に遭うことがあります。
この事態を受けて、中小企業庁はM&Aに関するガイドラインを改訂し、トラブル事例やリスクへの注意を促しています。
経営者がM&Aを検討する際には、十分な情報を確認することが大切です。
さらに、信頼できる専門家に相談することで、より安全な取引を進められるでしょう。
本記事では、以下の8つのトラブルと、その対処法について解説していきます。
- 仲介業者に関するトラブル
- 許認可に関するトラブル
- 情報開示に関するトラブル
- 財務・会計に関するトラブル
- 法務・契約に関するトラブル
- デューデリジェンス(買収監査)の不備
- 人材に関するトラブル
- M&A後の統合に関するトラブル
それでは、順番に見ていきましょう。
中小企業M&Aトラブル:準備段階のトラブル対処法

まず、M&Aの準備段階で注意すべきトラブルを紹介します。
1:仲介業者に関するトラブル
M&A準備段階で発生する1つ目のトラブルは、M&A仲介業者に関する問題です。
仲介業者は、売り手と買い手を結びつける重要な役割を担っています。
しかし、業者選びを誤ると交渉が滞り、スムーズに進まなくなることも少なくありません。
その結果、時間やコストを無駄にする可能性があるため、業者選定は慎重に行う必要があります。
たとえば、仲介業者を通じて事業売却を進めても、適切な買い手が見つからず、交渉が長引くことがあります。
さらに、業者から十分な情報が提供されない場合、売り手は買い手の資金力や事業内容を正確に把握できず、結果的に契約が成立しないこともあります。
特に、M&Aの仲介業者は、売り手と買い手の両者がクライアントといういびつな契約形態で、利益相反ともいえるものです。
そのため、売り手や買い手のそれぞれの意向を優先されない場合もあることが大きなトラブルの基といえるでしょう。
信頼できる業者の選び方と専門家の助言
このようなトラブルを防ぐためには、信頼できる仲介業者を選ぶことが欠かせません。
まずは複数の業者を比較し、実績や過去のM&A事例を確認するのがポイントです。
さらに、評判や口コミ、他社からの紹介も参考にするとよいでしょう。手数料の安さだけで決めるのではなく、業者のサポート体制や提供されるサービスの内容もしっかり確認しておく必要があります。
また、仲介業者に頼りすぎるのではなく、自社でも事業価値やM&Aの基本知識を持っておくことが大切です。
こうすることで、悪質な業者を避けることができるでしょう。
加えて、信頼できる第三者の専門家、たとえば弁護士や会計士、M&Aアドバイザーに相談するのも効果的です。
専門家の助言を受けることで、トラブルを未然に防ぎながら安心して進めることができるでしょう。
2:許認可に関するトラブル
M&A準備段階で発生する2つ目のトラブルは、許認可に関連する問題です。
許認可は、特定の事業を運営する際に必要な法的手続きです。
これが適切に取得されていない場合、買収後に事業をスムーズに進めることが難しくなります。
たとえば、飲食業の企業がM&Aを進める際、買収先が食品衛生の許認可を取得していない場合、買収後に営業停止となることが想像できます。
このようなトラブルを防ぐためには、M&Aの準備段階で許認可に関する調査を徹底し、事業継続に問題がないか確認することが欠かせません。
また、許認可の取得に時間がかかる場合には、その手続きに必要な時間や費用を事前に見積もっておくことも重要です。
さらに、許認可に関する専門的な知識を持つ第三者、たとえば行政書士や弁護士に相談するのも良いでしょう。
彼らは、許認可の手続きや法的要件に精通しており、必要な書類の準備や手続きを円滑に進めるためのアドバイスを提供します。
これにより、手続きの遅延を避け、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
中小企業M&Aトラブル:M&A交渉中のトラブル対処法

続いて、M&A交渉中に注意すべきトラブルについて紹介します。
3:情報開示に関するトラブル
3つ目のトラブルは、M&A交渉中における情報開示に関する問題です。
売り手と買い手が正確な情報を共有できていない場合、後に大きな問題に発展することがあります。
たとえば、売り手が財務情報を十分に開示しなかった場合、買い手は企業の負債を正しく把握できません。
その結果、買収後に予期しなかった負債を抱えることになり、経営に重大な影響を与えることがあります。
このようなトラブルは、信頼関係を損なうだけでなく、取引の破談や経営の悪化にもつながる恐れがあります。
情報開示のトラブルを避けるためには、売り手が交渉の初期段階から正確な情報を提供することが不可欠です。
財務状況や契約の詳細、法的リスクに関する情報は、買い手が事業価値を正しく評価するために重要です。
また、買い手も必要な情報を積極的に求め、疑わしい点や不明な点があれば、早い段階で質問や確認を行うと良いでしょう。
具体的な対策としては、デューデリジェンス(買収監査)を徹底することが有効です。
財務や法務の専門家と協力し、すべての情報が漏れなく開示されているかを確認することで、リスクを最小限に抑えることができます。
また、買収契約には、後から情報の不備が見つかった場合に備えて、補償条項やペナルティを明記しておくことが効果的です。
これにより、万が一のトラブルにも対応できるでしょう。
4:財務・会計に関するトラブル
4つ目のトラブルは、財務や会計に関する問題です。
たとえば、ある中小企業が正確な財務データを提供できなかったため、買い手が予測していた利益と実際の利益が大きく異なり、最終的に交渉が破談となった事例があります。
このような問題は、提供された情報が不正確だったり、不適切な会計処理が行われていた場合に発生します。
この種のトラブルを防ぐためには、はじめに、財務や会計データを正確に整理することが大切です。
適切に情報を開示することで、買い手との信頼を築くことができます。
また、交渉に入る前に、専門家のサポートを受けて財務状況を確認することも効果的です。
これにより、買い手との信頼関係を強化し、よりスムーズに交渉を進めることができるでしょう。
5:法務・契約に関するトラブル
5つ目のトラブルは、契約に関する問題です。
M&Aでは契約内容が複雑になるため、契約条項を十分に理解していないと、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
たとえば、ある企業がM&A契約を結ぶ際、契約書に記載された『債務引き継ぎ』に関する条項を十分に理解せずにサインした結果、問題が発生しました。
買収後に、売り手側が抱えていた隠れた債務を買い手が負担することになり、予想外のコストが発生する可能性があります。
こうした法務・契約に関するトラブルを防ぐためには、契約書の内容を事前に詳細に確認することが不可欠です。
曖昧な条項や不明確な条件が見つかれば、早い段階で解決することが求められます。
特に、売り手が抱える債務や訴訟リスク、重要な契約内容は、契約書にしっかりと明記する必要があります。
双方の義務や責任を明確にしておくことで、後のトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
6:デューデリジェンス(買収監査)の不備
6つ目のトラブルは、デューデリジェンス(買収監査)が不十分であることです。
デューデリジェンスとは、買収対象企業の財務や法務、税務などを詳しく調べ、隠れたリスクや問題を発見するための重要なプロセスです。
この調査が不十分なまま買収を進めてしまうと、後で予期しなかった負債が発覚することがあります。
その結果として、思いがけない大きな借金を抱えるリスクが生じる可能性があります。
買い手側は、財務諸表や過去の取引、契約内容、従業員の状況などを細かく確認し、リスクを最小限に抑える努力が求められます。
また、デューデリジェンスが不十分だった場合に備えて、契約書に補償条項を設けておくことも効果的です。
たとえば、買収後に隠れた負債や問題が見つかった場合、売り手にその責任を負わせる条項を契約に盛り込むことで、買い手は損失を避けることができます。
この補償条項は、後に発生するリスクを抑えるための重要な安全策といえるでしょう。
中小企業M&Aトラブル:M&A完了後のトラブル対処法

次に紹介するのは、M&A完了後に注意すべきトラブルです。
7:人材に関するトラブル
7つ目のトラブルは、M&A完了後に起こりうる人材に関する問題です。
M&A後、従業員が新しい経営方針や手法に不安を感じ、退職することがあります。
買収側は重要なスキルやノウハウを持つ従業員を失い、事業運営に大きな影響を及ぼす可能性も考えられます。
こうしたトラブルを避けるには、M&A後の早い段階で、従業員と十分なコミュニケーションを取ることが欠かせません。
従業員が新しい経営体制に安心できるよう、会社のビジョンや方針を明確に示すことが大切です。
特に、企業文化が異なる場合は、その違いを理解し、両社が歩み寄れる環境を整えることが成功へのカギとなります。
さらに、M&A後には従業員の役割や待遇が変わることもあります。
これをしっかり説明しないと、不安や不満が高まり、モチベーションが低下したり、最悪の場合、退職につながることも考えられます。
役割や待遇の変更については、事前にしっかり説明し、納得を得ることが何より重要です。
8:M&A後の統合に関するトラブル
8つ目のトラブルは、統合プロセスに関する問題です。
いわゆるPMI(ポストマージャ―インテグレーション)と呼ばれるもので、多くの案件でこのPMIの難しさを感じるようです。
特に、システムや業務の統合がスムーズに進まないケースが見受けられます。
買収先と買収側のシステムや業務プロセスに大きな違いがある場合に発生しやすいです。
例えば、買収先が古い管理システムを使っている場合、買収側が最新のシステムに移行しようとしても、データ移行がうまく進まず、結果的に業務に遅延が発生することがあります。
このような問題を回避するためには、M&A前に両社のシステムや業務プロセスを詳しく分析し、違いを把握することが重要です。
その上で、詳細な移行計画を立て、データ移行がスムーズに進むように準備を整えましょう。
特に、システムのテストや試験運用を行い、事前に問題がないか確認することが効果的です。
統合プロセスがうまく進まない場合には、計画を柔軟に見直すことも大切です。
また、専門家の助言を仰ぐことで、業務統合に伴うリスクを最小限に抑え、買収後の事業を順調に進めることができるでしょう。
中小企業M&Aトラブル まとめ

中小企業のM&Aでは、事前準備に加え、トラブルが発生した際の対応策を理解しておくことが重要です。
特に、M&A仲介業者の選定ミスや情報開示の不備は、深刻な問題を引き起こす可能性があります。
そのため、リスク回避のためには信頼できるアドバイザーの助言を得ながら、慎重に進めることが求められます。
当社では、M&Aを検討している企業や、新規事業としてM&Aを検討される経営者に向けに、個別コンサルティングを提供しています。(M&A仲介は行っておりません)
M&Aを通じて起業を目指している方の支援やM&A業界に就職・転職したいと考えている方にも最適な情報をご提供し、サポートを行っています。
さらに、M&Aに関するオンラインスクールも開講していますので、ご興味のある方は、ぜひLINEにご登録ください。
インターネットの黎明期から20年間マーケターとして活躍
ウマ娘のサイバーエージェント出身
世界的No.1コンサルティング会社、大手保険会社、大手損保会社、大手人材系上場企業など多様な業種のクライアントに対してマーケティングナレッジを活用して課題解決に貢献する
特に、「顧客設定」=「ペルソナ設定」において独自ナレッジを活用し、クライアントビジネスを成功に導く
ペルソナ設定だけで年間1億円の利益創出
ペルソナ設定だけでM&Aでたった1年で投資回収率(ROI)15倍達成